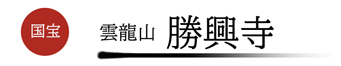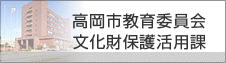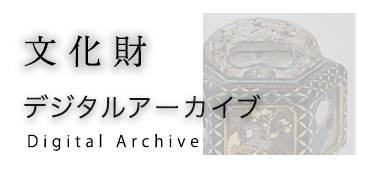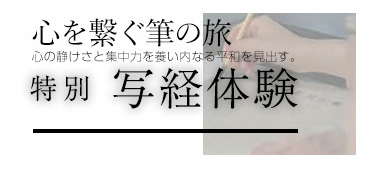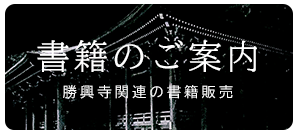勝興寺の歴史
History
6) 文化財の指定
 勝興寺が天正12年(1584)に現在地に移ってきて以来、江戸時代を通じて建立された建造物群が現在でもほぼ残されているばかりではなく、境内地もその当時から変化は見られません。真宗王国富山にあっても他に類を見ない完備した伽藍を有し、全国的にも傑出した境内の歴史的景観をよく残しています。境内には16棟の歴史的建造物が展開されていますが、これらの建造物は門徒衆の寄進と加賀前田家や本願寺の積極的な関与によって整備され、いずれも極めて質が高いと評価されています。
勝興寺が天正12年(1584)に現在地に移ってきて以来、江戸時代を通じて建立された建造物群が現在でもほぼ残されているばかりではなく、境内地もその当時から変化は見られません。真宗王国富山にあっても他に類を見ない完備した伽藍を有し、全国的にも傑出した境内の歴史的景観をよく残しています。境内には16棟の歴史的建造物が展開されていますが、これらの建造物は門徒衆の寄進と加賀前田家や本願寺の積極的な関与によって整備され、いずれも極めて質が高いと評価されています。
現在、「本堂」と「大広間及び式台」の2棟が国宝、経堂、鼓堂、宝蔵、御霊屋の堂舎群、書院及び奥書院、御内仏、台所の殿舎群、総門、唐門、式台門の計10棟が重要文化財に指定されています。この他、文化財指定はされていませんが、いずれも江戸時代の建造物として鐘楼、土蔵2棟、手水屋が残されています。
文化財指定の経緯は以下のとおりです。まず昭和63年1月に「本堂」と「唐門」の2棟が重要文化財に指定されました。その後平成8年9月に、横浜国立大学教授の関口欣也氏(故人)による学術調査報告書『越中勝興寺伽藍』が刊行され、その研究成果として平成7年12月には「経堂」、「鼓堂」、「宝蔵」、「御霊屋」の諸堂4棟、「大広間及び式台」、「書院及び奥書院」、「台所」、「御内仏」の殿舎4棟、そして「総門」、「式台門」の2棟の計10棟が重要文化財に追加指定され、指定件数は合計12棟となりました。
平成10年(1998)から23年間かけた「平成・令和の大修理」の施工中の平成31年3月には、東京藝術大学の光井渉教授による『勝興寺境内の文化財的価値に関する調査研究報告書』が刊行され、その成果によって令和4年12月に「本堂」と「大広間及び式台」の2棟が国宝に昇格指定となったのです。