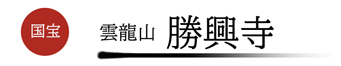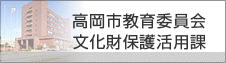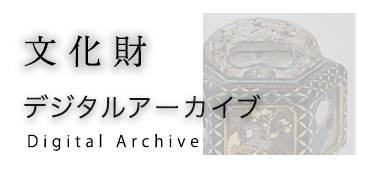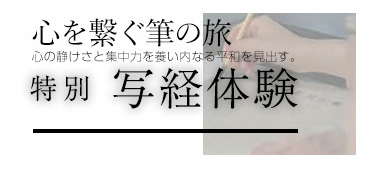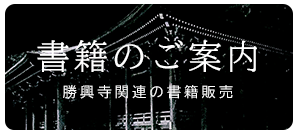勝興寺の歴史
History
7) 保存修理事業
第Ⅰ期保存修理事業(本堂)
勝興寺の建造物はいずれも経年の痛みが顕著で早急な保存修理が望まれていましたが、平成10年(1998)年から平成17年3月までの7年間の工期で第Ⅰ期保存修理事業として本堂の半解体修理が始まりました。 主な現状変更としては、修理前の屋根は桟瓦葺であったものが、痕跡調査の成果により原状はこけら葺の上に鉛板が葺いてあったことが判明しました。しかし、鉛の鉱毒による周囲の環境への悪影響を考慮し、今回の復原修理では鉛の風合いに近い亜鉛合金で修理を行いました。
第Ⅱ期保存修理事業(大広間及び式台ほか11棟)
平成17年度から第Ⅱ期保存修理事業として残り11棟の保存修理が始まりました。 当初は平成29年度までの13年間の修理計画が立てられました。しかし、本堂から大広間に繋がる廊下が礎石の存在によって確認されたため本堂北廊下として復元されたこと、また埋蔵文化財の調査、防災設備工事の拡大及び耐震診断やそれに伴う耐震補強工事などの計画変更により3年間の事業延長が認められ、最終的には第Ⅱ期保存修理事業は16年間となり、工期全体としては23年間の大修理となったのです。 なお、各建造物の主な現状変更の内容は以下のとおりです。
| ① 大広間 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更、玄関向拝を撤去 |
|---|---|
| ② 式台 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更、脇玄関2か所及び勝手玄関を復原 |
| ③ 書院 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更、12畳分の畳を板の間に復原、板の間と畳の間の間仕切及び床の間などを撤去、書院のいちばん西側の部屋は板の間に復原、書院から台所に繋がる廊下を整備 |
| ④ 奥書院 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更、茶室を撤去 |
| ⑤ 御内仏 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更 |
| ⑥ 台所 | 大屋根の棟高を下げて屋根勾配を緩くし、桟瓦葺を石置き屋根の板葺に変更のうえ鉄板で養生 |
| ⑦ 御霊屋 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更 |
| ⑧ 経堂 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更、輪蔵の高欄の擬宝珠を整備 |
| ⑨ 宝蔵 | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更、正面石段に擬宝珠柱を整備 |
| ⑩ 鼓堂 | 屋根を桟瓦及び本瓦葺からこけら葺に変更 |
| ⑪ 唐門 | 屋根を銅板葺から檜皮葺に変更 |
| ⑫ 式台門(番所を含む) | 屋根を桟瓦葺からこけら葺に変更、戸口の蹴放を復原 |
| ⑬ 総門 | 無し |