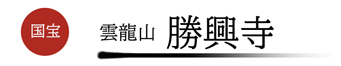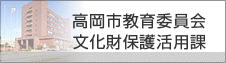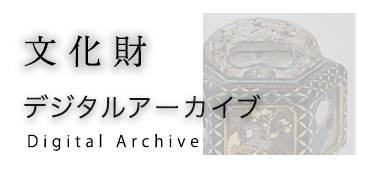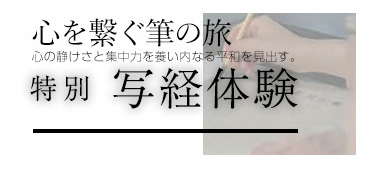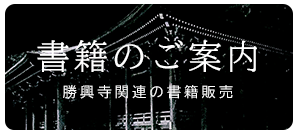勝興寺の歴史
History
5) 江戸時代後期から明治時代まで
 前田治脩が死去して以降は、加賀藩や前田家関係の史料に勝興寺の記述はほとんど見られなくなります。治脩の時代までは基本的に加賀藩の手厚い援助のもとで勝興寺の維持運営がなされてきましたが、文化2年(1805)に竣工した経堂については、高岡商人で構成される「高岡尼講中」が享和元年(1801)から行った資金調達によって建設されており、19世紀に入ると門徒からの寄進も重要な資金となっていたことが確認でき、江戸時代後期に勝興寺は最盛期を迎えます。
前田治脩が死去して以降は、加賀藩や前田家関係の史料に勝興寺の記述はほとんど見られなくなります。治脩の時代までは基本的に加賀藩の手厚い援助のもとで勝興寺の維持運営がなされてきましたが、文化2年(1805)に竣工した経堂については、高岡商人で構成される「高岡尼講中」が享和元年(1801)から行った資金調達によって建設されており、19世紀に入ると門徒からの寄進も重要な資金となっていたことが確認でき、江戸時代後期に勝興寺は最盛期を迎えます。
明治時代以降には寺領を失い、同時に加賀藩や前田家からの援助も失うことになりましたが、真宗王国富山にあって門徒衆からの寄進は相変わらず旺盛であったため、新規の大造営は行われないものの、本堂の修理など大伽藍の維持は継続して行われています。他の大名菩提寺が明治期に急速に衰退していったのとは対照的に、境内地の伽藍を構成する建造物群が今日まで維持・継承されてきたことは、ひとえに門徒衆の献身的な寄進や貢献によるものであると言えるのです。