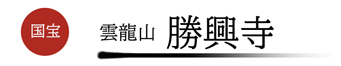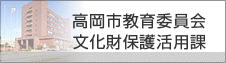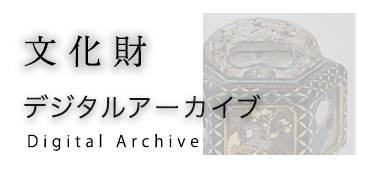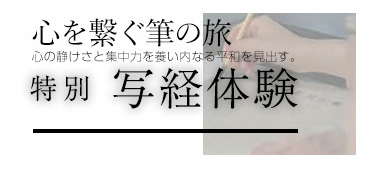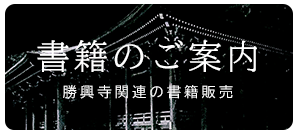勝興寺の歴史
History
4) 尊丸(前田治脩)の入寺と本堂の建設
 前田治脩は、延享2年(1745)に加賀前田家六代当主の前田吉徳の十男として生まれ、幼いころ勝興寺に入寺し十三代住持の法暢
前田治脩は、延享2年(1745)に加賀前田家六代当主の前田吉徳の十男として生まれ、幼いころ勝興寺に入寺し十三代住持の法暢
法暢の室は本願寺の養女であり、良昌の時代以後に疎遠となっていた加賀前田家と勝興寺との関係が再び緊密になる契機となります。法暢の還俗後に勝興寺十四代住持となった法薫は本願寺十七世法如の実子であり、その室の芳明は前田治脩の養女であるため、勝興寺と加賀藩との関係はさらに深化し最高の状態に至りました。
この体制のもと、勝興寺は西本願寺の阿弥陀堂に匹敵する現本堂の建設に着手しています。建設体制は、西本願寺棟梁の水口伊豆が本堂の基本設計を、加賀藩御大工の山上善五郎が監督・指導、そして地元大工の滝川喜右衛門が棟梁をそれぞれ担当しました。また建設資金については、加賀藩からの材料や資金の援助、西本願寺からは勝興寺に対する門徒の寄進を促す「勧募
江戸期初頭の九代住持良昌の時に大広間の建設が加賀藩主導で行われたのに対して、本堂建設の際には、本願寺、加賀藩及び勝興寺門徒という三位一体の協力体制のもとで行われたのです。