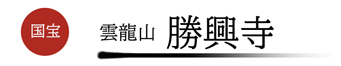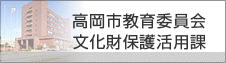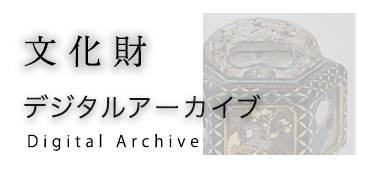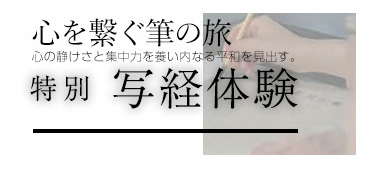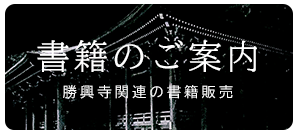勝興寺の歴史
History
3) 良昌の時代
 良昌は本願寺から勝興寺に入寺した勝興寺九代住持です。その良昌に対して前田利光(後の利常)は慶安2年(1649)に寺領の加増や自身の養女を輿入れさせただけでなく、それまでの領内の寺社の階層を改めて、勝興寺を『別格扱い』にして支援しました。ちなみに前田利常の室である珠姫は徳川秀忠の娘なので、勝興寺は形式的にではありますが徳川将軍家とも連なることとなりました。
良昌は本願寺から勝興寺に入寺した勝興寺九代住持です。その良昌に対して前田利光(後の利常)は慶安2年(1649)に寺領の加増や自身の養女を輿入れさせただけでなく、それまでの領内の寺社の階層を改めて、勝興寺を『別格扱い』にして支援しました。ちなみに前田利常の室である珠姫は徳川秀忠の娘なので、勝興寺は形式的にではありますが徳川将軍家とも連なることとなりました。
この時期に本願寺及び加賀藩との緊密な関係のもとで建設活動が実施されています。まず、慶安3年(1650)に本願寺が勝興寺への勧進を指示し、承応2年(1653)に本願寺十三世の光圓(良如)から小松中納言(前田利常)に宛てた礼状で、勝興寺の「過分の屋敷」に言及しています。このことから、慶安期には浄土真宗教団による勧進に加えて加賀前田家からの直接的な支援を受けて建設活動が実施され、承応2年(1653)には完成していたことになります。その建設事業の内容は「屋敷」あるいは婚礼と関係する普請であり住宅系の殿舎群であることは確実で、これが国宝の大広間が承応2年(1653)の建立とする根拠となっています。
この時期の加賀藩内における建設事業を俯瞰すると、勝興寺の殿舎群の建設と並行して高岡市内のもう一つの国宝である瑞龍寺の造営にも着手し、国宝の法堂が明暦元年(1655)、重要文化財の総門と大茶堂が明暦頃、国宝の仏殿が万治2年(1659)に竣工しています。すなわち17世紀中頃に前田利常の主導のもとで、勝興寺と瑞龍寺の両伽藍の造営が行われていたことになるのです。