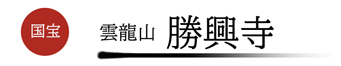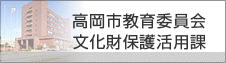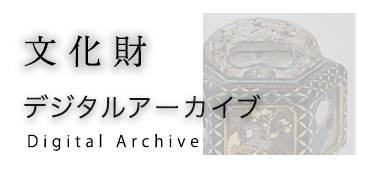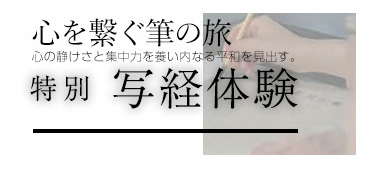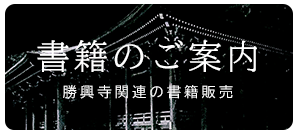勝興寺の歴史
History
2) 江戸時代初期の勝興寺
 天正13年(1584)に現在の伏木古国府に移転した時に住持を勤めた勝興寺六代の顕幸は、慶長9年(1604)に没しました。その後を継いだ七代顕称は、本願寺の東西分裂の際に大谷派(東)についた「摂州教行寺」から入寺しており、本願寺派につくことを決定した勝興寺において顕称は立場をなくし、法式が乱れ断絶の危機にあったとの記述がみられます(「加越能寺社由来」貞享2年(1685)2月28日付書上)。
天正13年(1584)に現在の伏木古国府に移転した時に住持を勤めた勝興寺六代の顕幸は、慶長9年(1604)に没しました。その後を継いだ七代顕称は、本願寺の東西分裂の際に大谷派(東)についた「摂州教行寺」から入寺しており、本願寺派につくことを決定した勝興寺において顕称は立場をなくし、法式が乱れ断絶の危機にあったとの記述がみられます(「加越能寺社由来」貞享2年(1685)2月28日付書上)。
このことから、17世紀初頭の慶長・元和の時期にかけての勝興寺は、加賀前田家や混乱の最中にあった本願寺との関係は希薄であり、勝興寺自らの力で境内の整備が行われていたと考えられ、現在のような壮麗な建築群を建設する経済力があったと考えることはできません。また、本願寺法主や藩主の御成りのための殿舎群を必要とする状況ではなかったことから、元和期までの勝興寺は殿舎群を備えておらず、小規模な本堂などの堂舎と庫裏などで構成される境内であったと考えられています。