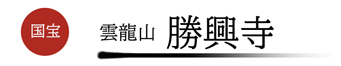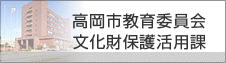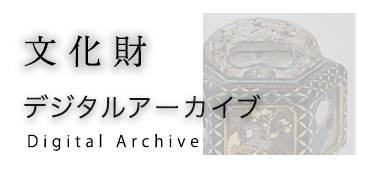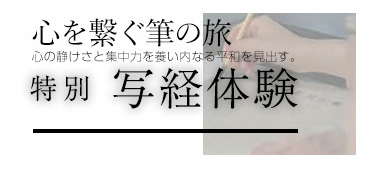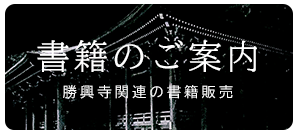勝興寺の歴史
History
1) 創建から現在の地への移転
 雲龍山勝興寺は、文明3年(1471)に本願寺八世蓮如上人が創建した土山御坊(南砺市福光)を起源とする浄土真宗の古刹です。以後、明応3年(1494)に高木場(南砺市高窪)に移転し、永正14年(1517)には佐渡国笹川の廃寺となっていた順徳上皇の勅願所である殊勝誓願興行寺の寺号を受け継いで勝興寺となりました。さらに永正16年(1519)の安養寺(小矢部市末友)への移転を経て、現在の高岡市伏木古国府に寺基を構えたのが天正12年(1584)のことです。
雲龍山勝興寺は、文明3年(1471)に本願寺八世蓮如上人が創建した土山御坊(南砺市福光)を起源とする浄土真宗の古刹です。以後、明応3年(1494)に高木場(南砺市高窪)に移転し、永正14年(1517)には佐渡国笹川の廃寺となっていた順徳上皇の勅願所である殊勝誓願興行寺の寺号を受け継いで勝興寺となりました。さらに永正16年(1519)の安養寺(小矢部市末友)への移転を経て、現在の高岡市伏木古国府に寺基を構えたのが天正12年(1584)のことです。
この地への移転の経緯は、当時越中を支配していた佐々成政が勝興寺の古国府移転と再興を認め勝興寺に折紙を与えると同時に、その家臣である守山城主の神保氏張からは古国府の一円の土地を寄進するなどの制札を発せられたことによるものです。
移転の翌年の天正13年(1585)に佐々成政は羽柴秀吉に敗北して越中を退去し、同年7月に秀吉が禁制を発したのに続き、秀吉と成政に代わって越中の支配者となった前田利勝(後の利長)も禁制を与えて勝興寺の保護と既得権を安堵しました。
このように、勝興寺は16世紀末までは一向一揆を主導して時の権力に反抗し、周辺地域を支配する戦国期の浄土真宗寺院の体質を受け継ぐ存在でしたが、伏木古国府への移転後は、近世の絶対権力の出現と成長の中で検地を受け入れて一円の支配権を失い、境内や寺領を限定されて近世寺院へと変貌を遂げていったのです。